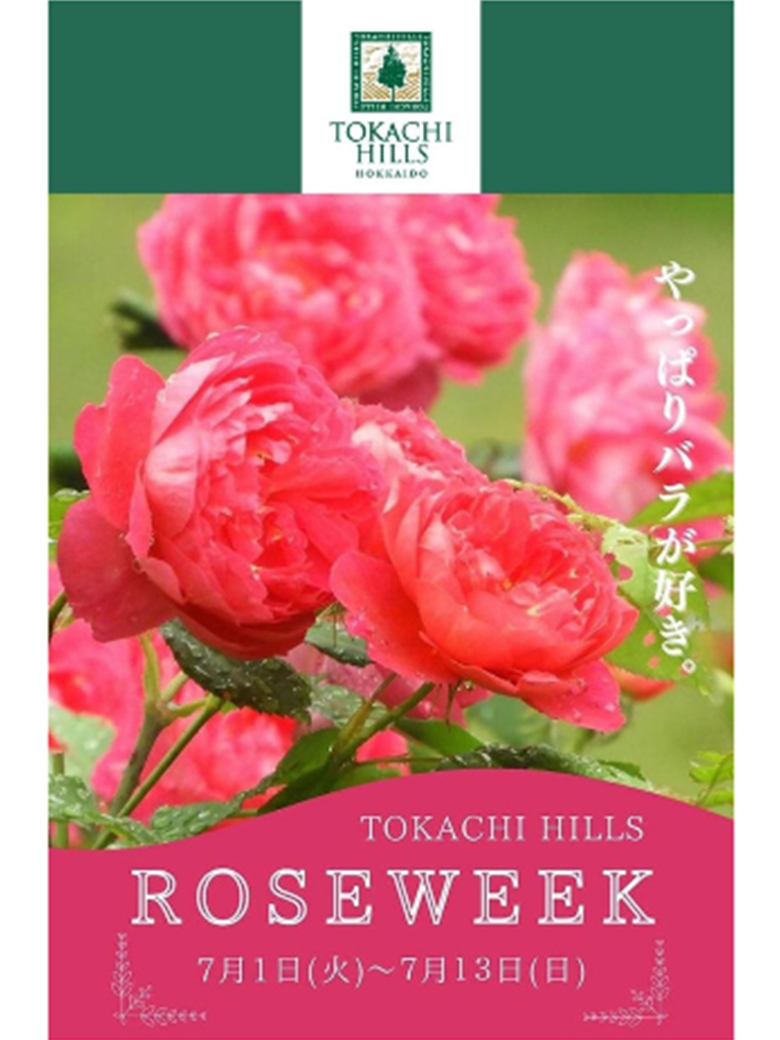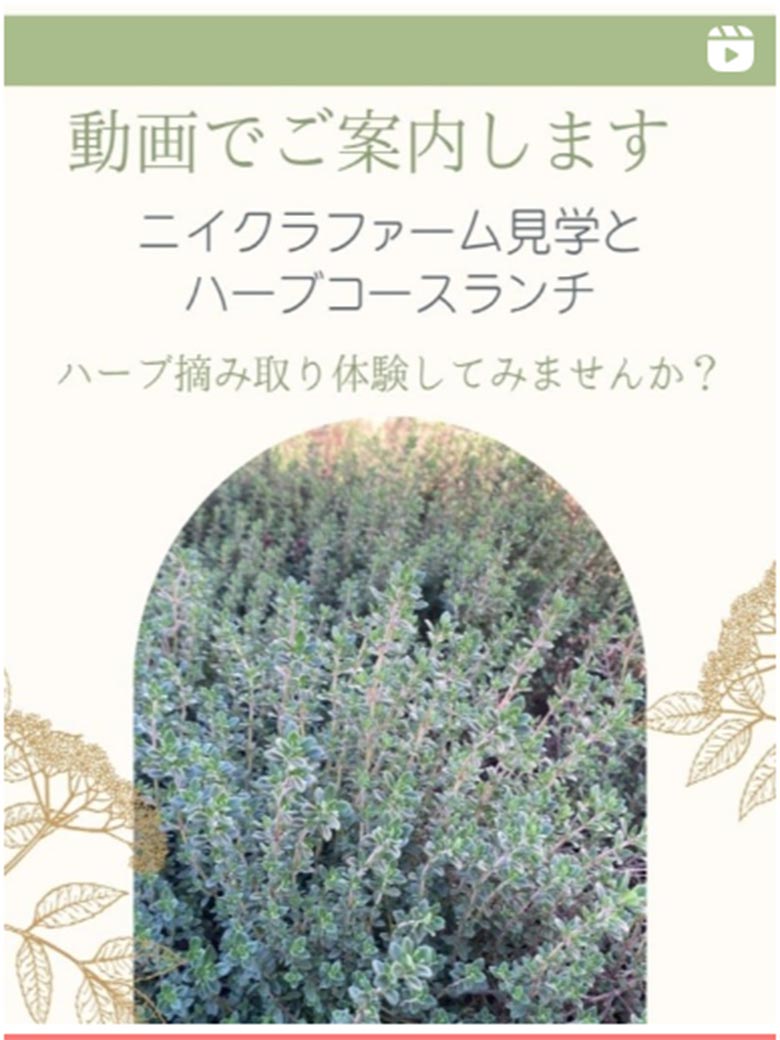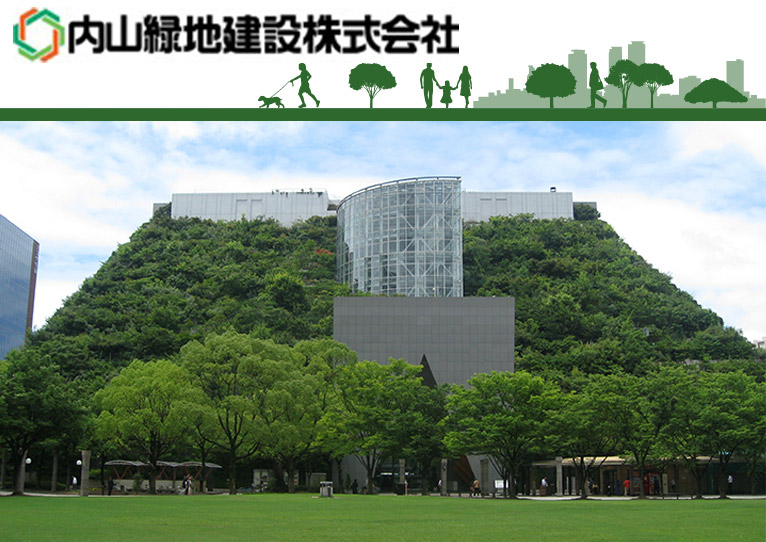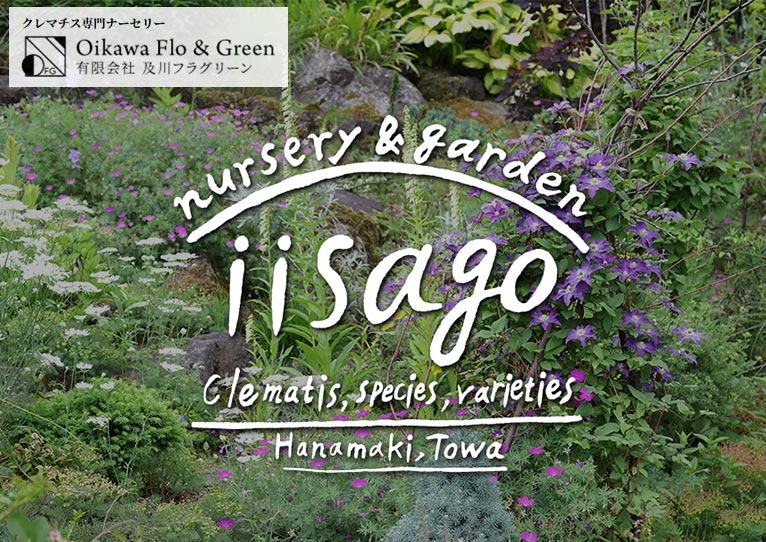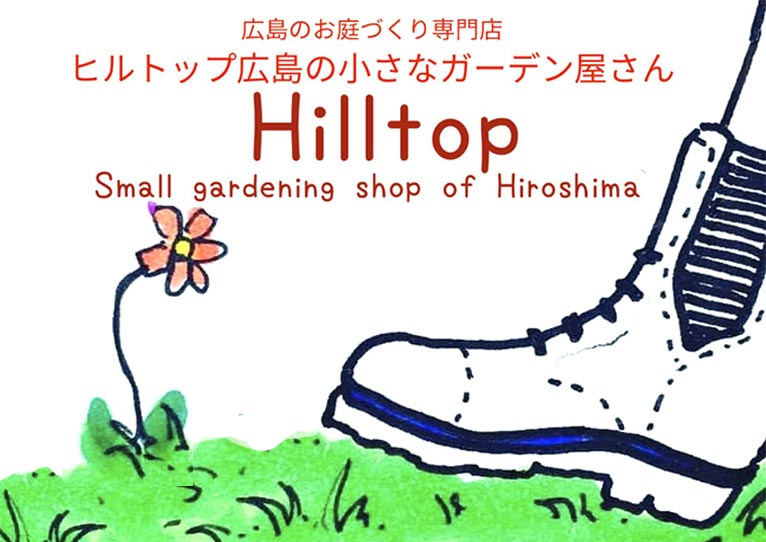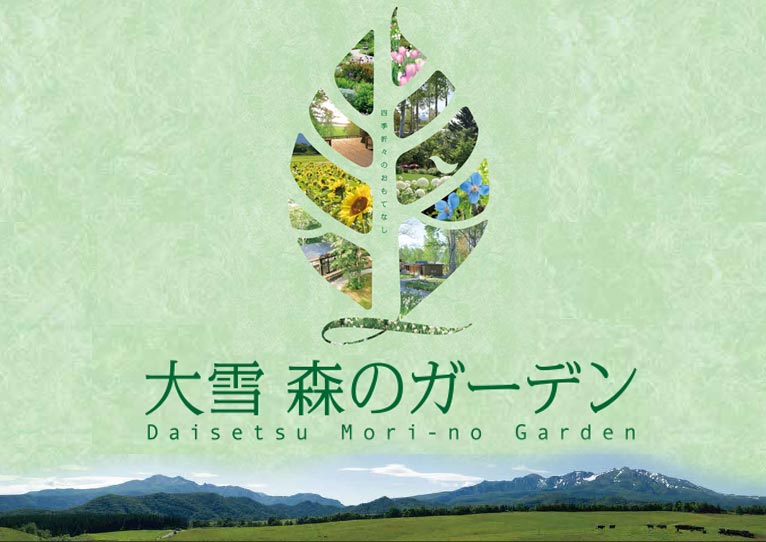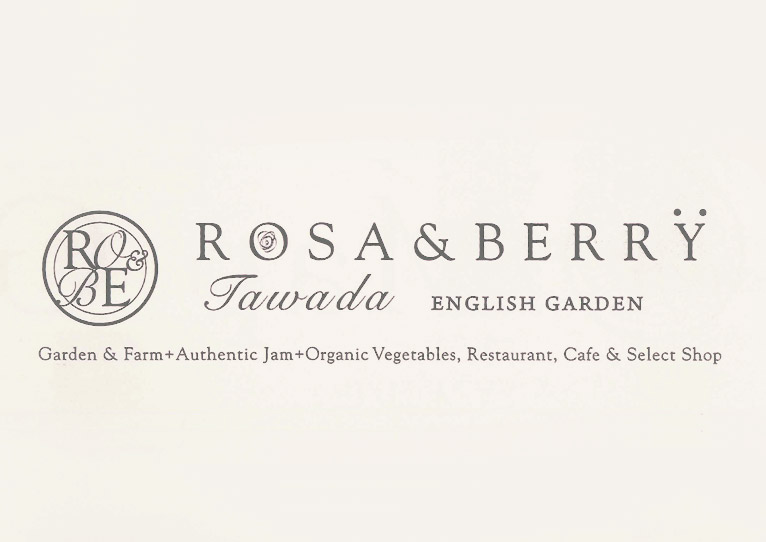ガーデニング・園芸を楽しむJGNのコミュニティサイト
植物百般 インタビュー
「石はカッコイイ」(その3)
JGN理事 高崎設計室代表取締役 髙﨑 康隆

| 庭づくりの重要な素材として使われる石。世界中の人々の心をとらえる伝統的な日本庭園の石組は、誰でも一度はご覧になったことがあるはずですが、草花や樹木といった植物素材に比べると少々ハードルが高く感じられるかもしれません。「難しく考えずに、まずは石を見て想像を広げてみましょう」と話す髙﨑康隆理事。自身の石との出会いから、インタビューが始まります。 |
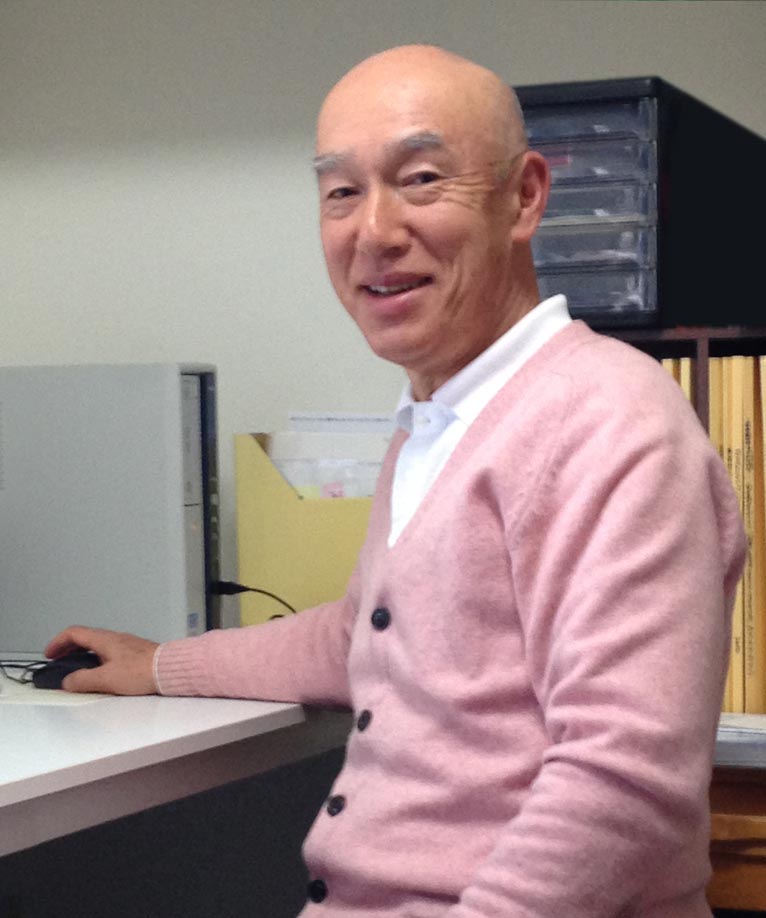 ► 髙﨑 康隆(たかさき やすたか) 高崎設計室代表取締役 石組師 京都造形芸術大学講師 京都で古庭園の調査・測量に従事。造園家 中島健氏に師事。伝統庭園とともに草花を取り込んだ庭園を手がけ、職人と設計者両方の仕事を体験する。著書・監修に「庭仕事の庭石テクニック」、「原色庭石大事典」(共に誠文堂新光社)など多数。JGN理事。 |
JGN事務局スタッフ(以下JGNで表記):
少しだけ、髙﨑さんの石コレクションをご紹介くださいますか?
髙﨑:
いいですよ。まずはこちら。この座布団は、妻に作ってもらいました。完全をちょっと崩すと言う、禅の思想のようなものを感じます。ひっくり返した面もおもしろい。こんな風に小さなウサギの置物を置くのは「野原に一筋の流れがあって、そこに遊ぶウサギ」と見立てる水石の楽しみ方です。

本当に水の流れと野原に見えてくるから不思議。ウサギも一興です。
JGN:
本当ですね。実際にはないのだけれど、月の姿が目に浮かびました。
髙﨑:
想像が広がるでしょう?続いてこちらはどうでしょう。どこで拾ったかは覚えてないのです。ベランダにしばらくほっておいたけれど、ある日手に取ったらなかなかいいなと。盆栽美術館でこの鉢をみつけて、置いてみたら良いんですよね。
►ログイン
JGN会員になるとログインするための【発行PW】を記載したメールをお送りします。
会員様で【発行PW】がわからない場合はwebmaster2@gardenersnet.or.jpまでご連絡ください。 ►会員になるにはこちらから詳細をご覧ください。